対話形式の掲載にしていますので、ぜひ見てください。
今回は向吉先生の作品を通して、
不動明王についてお聞きします。
ありがとうございます!
今回も先生の仏様、そして人の願いや思いと向き合う姿勢を勉強させていただきながら、色々とお聞きします。
こちらの不動明王様は青い不動明王様ですが、赤など他の色をしたお不動さんがいらっしゃいますね。
私は赤いお不動さんをよく見かけます。
一番古いお不動さんは、この様な青色です。
青不動といって これが一番最初、中国から日本に伝わった時のお不動さんの色で、一番多いお不動さん。
で、次が赤不動となり、信号機じゃないですが(笑)、黄不動っていうのもあります。
黄金色っていう言い方をしますが、こちらは滋賀県の三井寺(みいでら)さんにいらっしゃいます。
お不動さんの特徴の一つとして、
表情は厳しくも、ぽちゃぽちゃとした体つきで丸く丸く作るのが普通なんですが、
こちらの黄不動明王は、腕も筋肉の筋を入れたり、足も仁王さんみたいな形になっています。
実は、この様なお姿は不動明王としての作り方としては、タブーなんです。
ですが、絵像が最初にあったので、その絵像と同じように彫像したもので、数は少ないですが私も彫ったことがあります。
特別に製作中の作品を見せていただきました。
浮世絵にもあるようにぐっと足に力を入れているところなど、
表情からだけでなく、体に力が入っていて何かに耐えているという様にも感じられますね。
表情は、厳しく独特のお顔をされています。
向かって左側の目は見開き、右側の目は半分閉じています。
これは、天地眼(てんちがん)って言って、見開いてる方が天を向き、閉じている方が地を向いています。
この天地眼、インド、チベットから中国へと伝わり、空海さんが日本に伝えた時には両方の目をむいて怒りを表してる形相で、髪も巻毛じゃなくて、綺麗になでてあるような髪の毛です。
その日本に伝わった一番最初の不動明王は、京都の教王護国寺(東寺)さんの
立体曼荼羅で3メートル半から4メートルぐらいの大きさのもの※1が今も残っています。
現代の主流は、今回の青不動明王様の様な「巻髪で天地眼」となっています。
それは、最澄さん、空海さんの時代よりも数100年後に天台の僧侶たちが勉強しに行った際、
中国でも変遷があって、両方を目を見開いたお不動さんよりももっと いかつい顔で、もっといりきのある形に変化していた。
そのお不動さんが今に残り、空海さんが開宗した真言宗でも同じように「巻髪で天地眼」のお不動さんを拝んでいます。
お不動さんの厳しい表情、怖いお顔。
私も子どもながらにその存在の大きさを感じ、自然に手を合わせた時のことを思い出しました。
たくさんの願いや思いが籠っている、そんな存在の様に思います。
その怖いと感じる感覚、それを言い換えるとすると
「畏怖(いふ)」といった言い方になると思います。
恐れ慄(おのの)くではなくて、崇め奉るという意味も含めた言葉です。
怖さを感じ、神々しさを感じるっていう言い方を私たちはしています。
手を合わせることは、人生の中の一つの道徳的なたしなみで財産だと思います。
いろんな方と共にお迎えしていただいたお不動さんですが、 その厳しい表情に全くもって同じものがないと言える仏様です。
それは、私がとにかく依頼される方のいろんなお話を聞いて彫りますので、 同じ人生は絶対ないですから、同じものにはなりません。
我々 仏師というのは、
その役目を負っていて ”生きた信仰” が、
そこになければならない。
その人の人間性であったり、
生い立ちであったり、
修行の成り立ちであったり、
それで変わってくるのは当然なんですけど、
その人の同じ言葉を同じ様に仏師二人が聞いても、
受け取り方が違ってくるはずなので、
やっぱり出来上がりも変わってきますよね。
だから、今のお話に対して、私はこう感じて、こう作りましたとなって、 その方やその方を頼りにされる信者さんが見ている お不動さんを迎えることになります。
お不動さんの表情だけはやっぱり実際に拝んでいる方々の言葉というのが一番沁みました。
お不動さんを迎え入れるにあたって、お話を聞くと、
もうこんなこんなこんな・・・って1時間も2時間もお話をされて、その深さをこちらが受け取れるかどうかっていうぐらいお話をされる方もいらっしゃいます。
行者さんにしても、お坊さんにしても、その方たちを頼ってくる信者さんがたくさんいらっしゃいます。
その方々は、本当に苦しいと思います。
苦しい行をしながら、
体の痛みとか火傷をしたりと苦しい。
ギリギリまで我慢して、
ギリギリまで一生懸命やってたけど、
本当にもう 本当にギリギリで、
もうあかん
(精神的にも限界で、どうにかなってしまいそう)となった時に、
神頼みというのもやっぱりあると思います。
「不動明王も我々と同じように苦しんで、
願いを聞き届けて欲しい。」
それを受け止める仏様っていうのは、
行者さんがよく言われる言葉なんですけど、
強さだけではなく、
如来の思いも受け継いでいて、
観音の優しさもあって、
しかも厳しいお顔だけど、
護摩の炎の向こう側にある表情がいくつも見える。
表情が、泣いているように見えたりもする。
そういう話を聞いた上で、
そんな表情に見えるのかどうか、
なんでだろうかと考えて、
私には、今はまだ分からないんですけど、
ただ、お話を聞く中で
「願成就院(がんじょうじゅいん)のお不動さん※の あのお顔は本当に拝みやすい」という言い方をされたので、
我々が求めるところの"炎の向こうで表情が動く可能性"として、手応えを感じています。
お不動さん以外の仏様の場合、
お燈明一本とかライティングをちゃんとしてあって決まった光に近い状態だと思いますが、お不動さんでは当たる光が一瞬一瞬で変わります。
炎は どんな形になるか分からない上、その炎越しで表情が毎回違って見えるでしょうし、それを行者の方は その一瞬一瞬を受け止めるわけです。
願成就院のお不動さんと同じように作っても、炎の動きとか炎の勢いとかでそういう風に見えない時もあるかもしれませんが、我々が参考にしているお不動さんです。
不動明王が、とても大きな存在であること。
一言ではもちろんのこと、言葉では言い表せないことが
そこにあって、圧倒されました。
やっぱりね、仏様それぞれの役割があるんだと思います。
だから400種類以上の仏さんがいてはるんだと思います。
その中の強さとか、みんなの悩みとか煩悩(ぼんのう)を
引き受けるトップの方が不動明王なんですね。
誰しも生きていたら、いろんな事でやっぱり変な汗をかいたり、精神的に追い込まれたということがあると思います。
今日まで何ともなかったのに、明日になったら、もしかしたら どえらい悩みを持ってしまう可能性もある。
現世の皆さんの苦しみ その受け取り方も多様化していると思います。
とにかく いろんなお話を聞いて彫るっていうのは、
やっぱり自分のライフワークで、特にお不動さんは、その役目を負っている我々も、苦しみに向き合います。
今回はとても重たい話だったでしょう(笑)。
(笑)
(適切な言葉が出ない)
先生が向き合う世界のほんの一部分ですが、
感じることができた様に思います。
”生きた信仰”と今の私たちが抱える苦しみ、
一人で抱えるだけではない受け止めてくれる存在。
大きな存在。
とても大切なことを気付かせていただきました。
ありがとうございました。
次回は、毘沙門天(びじゃもんてん)を
ピックアップします。
※1 不動明王(国宝)
空海さんが指導したであろう面立ち、造り方が当時のままで残っている。
先生が好きなお不動さんで不動明王の根本として参考にしている仏様。
※2 不動明王立像 国宝・運慶作
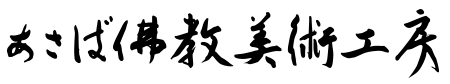


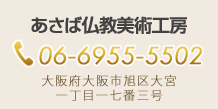











「お不動さん」で親しまれている不動明王は、
毎回違う表情で彫り出されます。
人生、その背負ってきている背景、その方の範疇や深さでお姿が変わる存在の仏様です。
今回は そのことも含めてお話しできればと思います。