対話形式の掲載にしていますので、ぜひ見てください。
今回は中村先生のこちらの作品、
孔雀明王についてお聞きします。
孔雀明王図
寸法 縦137.9cm × 横85.4cm
材質 絹本
所蔵先 個人蔵
孔雀が仏さまと一緒にいる姿をわたしは初めて見ました。
とてもユニークな姿なのですが、なぜ孔雀なのでしょうか?
インドでは、動物が住むところと人間が住むところが一緒なことが多く、そこにはネズミなど蛇が食べる餌があるので、近づいてきやすい。
そのため、毒蛇で亡くなる方はとても多かったと言われています。
孔雀の美しい姿、毒のある蛇を食べても耐性を持っていることが神格化される所以(ゆえん)ではないでしょうか。
たくさんの人が毒蛇に噛まれて命を落としていたんですね。
その蛇を食べてくれる孔雀は当時の人にとっては、とてもありがたい存在だったことがわかります。
蛇は昔から恐れられていたのですね。
蛇は他の宗教でも悪いイメージがありますね。
そうですね、仏教でもそういったイメージはあります。
日本でも蛇のような性格(粘着質)という言い回しや、あまり正直なことを言わないというイメージがありますね。
蛇にしては迷惑な話ですが、人間の潜在意識で怖いという認識が植え付けられているからこその言い回しなのではないかと思います。
例えば、猫のそばにきゅうりや細いホースが置いてあったら、気づいた瞬間に猫はびっくりして逃げるんですよ。
猫は、蛇がそばにいると早とちりしてしまうのですね。
人間にもそれぐらい『蛇は怖い』と深く根付いているものかもしれませんね。
わたしも蛇は怖いです。
草むらですっと現れる姿に冷や汗をかくことも何度かありました。
その蛇を食べる孔雀明王ですが、4つの手があるのですね。
それぞれ手に持っているものにも意味があると思うのですが、それぞれどういったことが表されているのでしょうか?
たくさんの手や顔がたくさんある仏さんがいらっしゃいますね。
十一面観音は、顔が11ある、手で多いものでは千手観音の千本。
千手観音はありとあらゆる願いや要望に応えてあげられる様にという姿を手や顔の数で表していると言われていますが、孔雀観音の手は4本です。
千手観音のようになんでもかんでも聞き入れてくれる仏さんとは違って、お約束や願いごとに特化して叶えてくれることを求め表現された仏さんです。
孔雀明王や仏さんの恩恵は持物(じもつ:持ち物の意)で表されていて、
蓮華(れんげ)は、寿命、命を永らえる、幸せになれるようにといった願いや極楽浄土(ごくらくじょうど)に生まれ変われますようにといった願いも込められています。
吉祥果(きちじょうか)は、体を正の(良い)状態に戻すという意味合いから薬としているのではないかと考えられています。
赤い実は、ざくろで子宝に恵まれるという意味です。
孔雀の羽は、負傷や動物に襲われないように、病気にならないようにという願いを表していると言われます。
孔雀明王様を拝むとこれらのご利益、願いを形にデザインされてきたんだと思います。
人々の暮らしに寄り添い、救いの手を差し伸べるそんな明王様なのですね。
でも、明王様でイメージするのは、怒っている顔、怖い顔なのですが、孔雀明王はとっても優しい顔なんですね。
そうですね。
唯一菩薩さんのお顔、お姫様の様な顔をしていますよね。
美しい孔雀と一緒に表れるお姿として、不動さんや愛染さんのように怖い顔をしている仏さんが上に乗っているイメージが湧かなかったんでしょうね。
優しい表情と見た目の優美さだけでなく、毒を制する力強さ。
明王と呼ばれるその尊格には、人々を力強く救う力を兼ね備えている、その様な人々の憧れがあるように感じました。
仏教の中では、孔雀以外にも動物が表されていますが、それらも同じ様な存在なのでしょうか?
そうですね。
神格化されている動物は聖獣(せいじゅう)とも呼ばれ、
孔雀以外にも象、獅子、龍などがいます。
中でも獅子や龍は、中国の四神(青龍・白虎・朱雀・玄武)と仏教が結びついています。
龍はもともと仏教にあったと言われていますが、インドでの龍は飛龍を指し、空を飛ぶ龍が発端。
中国の四神の青龍と結びついて、今の龍が出来上がっています。
また、獅子は白虎として表されています。
中国にライオンは生息していませんでしたが、虎はいるのでその姿から想像して表現されていました。
中国を通じて伝来する仏教で様々な解釈が行われてきたのですね。
日本と外国との違いというのも とても興味深いです。
まず、中国の孔雀はすごく凛々しく表現されていて、しかも大きいんです。
そこからは当時の中国の思想や強い願いを感じることができます。
人々の中にある煩悩や悪い心を自分自身で打ち負かす「降伏(ごうぶく)※1」。
孔雀の力強さ、凛々しさ、その姿が自らを律することのできる人になりたい、なれると力強く願っていたのではないかと計り知ることができます。
そういった神仏の威力(いりき)※2を聖獣を従えて現れる姿で表現したのではないかと思います。
他には、象の表現も日本では様子が異なります。
普賢(ふげん)菩薩の下にいる聖獣は象なんですね。
その象のモデルはインド象で、アフリカの象と比べると体も牙も小さいのが特徴です。
今のお話を聞いて、当時の人々の込められた思い、
-仏教世界をファンタジーとは違って、現実世界に存在させること- を心から願い、
全身全霊で取り組み続けたこと、それが永く受け継がれ今もなお残っていることの尊さを再発見できました。
今も昔も身近な人の幸せを願う気持ちは変わらないものです。
今ではしっかりと治すことができる結核や肺炎、昔は大病で死の病です。
普通の風邪でも子ども達の3人に2人は亡くなったと言われています。
だからこそ、無病息災(むびょうそくさい)の願いは とても切実なものでした。
鹿児島県に伝わる伝統的な儀式 七草祝いは、
数え年で7歳になった子どもの無病息災を願う行事です。
1月7日に晴れ着を着た子どもたちが神社に参拝し、七草粥を7軒の家で分けてもらうという風習があります。
よくぞ生き残ってくれたという気持ち、親や家族の一番の願いだったのではないでしょうか。
本当にそうですね!
込められた思いの深さを知ることができ、
お寺などに行く時には、今までとは違った洞察を持って体感することができそうです。
ぜひ、お寺巡りを楽しんでください!
今の子たちへのある特別授業で
「お寺に入ったことがない子は手を挙げて」と言うと
半数の子たちが手を挙げてびっくりしました。
わたしたちの小さいころは、よくお寺で遊んで怒られたこともありました。(笑)
時代と共に仏教への親しみ方も変化していますが、大切な人や自分自身の人生で必要な時に仏様の前で手を合わせることがあったら、
その時にたくさんの人が込めてきた思いも一緒に感じてもらいたいですね。
先生、今回もたくさんのことを教えていただいて本当にありがとうございました。
次回は、聖観音(しょうかんのん)をピックアップします。
※1 降伏(ごうぶく)
仏教読みで「ごうぶく」。
一般的な「こうふく」の意味は、外の敵に降参するという意味になりますが、
仏教では外にいる相手を倒すことではなく、自身の煩悩や悪い心を自身で打ち負かすことを意味しています。
※2 いりき
仏様には、私たちの認識を超えた力を具(そな)えているとされています。
それが「威神力(いじんりき)」であり、「威力(いりき)」「神力(じんりき)」などとも言われます。
※孔雀明王の持物(じもつ)について
●蓮華(れんげ)
寿命、命を永らえる、幸せになれるように、極楽浄土に生まれ変われますようにといった意味。
●吉祥果(きちじょうか)
みかんみたいなもので柑橘系の果物はビタミンが豊富で元気にしてくれることから、体を正の(良い)状態に戻すという意味合いから薬としているのではないか。
壺と一緒で解毒剤、お薬の意味合い。
今のようにビタミンやミネラルということは知られていないので、これを食べたら元気になるといったことやすっぱいものを食べたらすっきりするといったことそういったイメージを表していると考えられます。
●赤い実
ざくろ。子宝に恵まれますようにという願いを受け取ることを表しています。
中に実がたくさん(100〜200ぐらい)入っていることから子宝の象徴として。
今で言う家内安全、商売が代々繋がっていきますように。
●孔雀の羽
孔雀そのものの意で、悪魔退散・魔物退散。
蛇に襲われないように、負傷や動物に襲われないように、病気にならないようにという意味合いを持ちます。
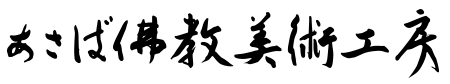


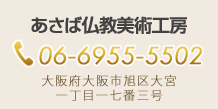








孔雀は、仏教発祥の地インドでは大事にされている鳥です。
孔雀はコブラなどの毒蛇を食べます。
中でもインドコブラは、噛まれたら象でもひとたまりもないくらいで人間なら1分も持たず絶命する毒を持っています。
そんな毒蛇を孔雀が食べるので「わぁ、孔雀が助けてくれた〜」と人は感じていたんですね。