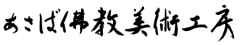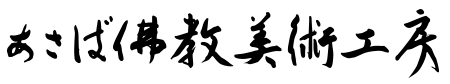対話形式の掲載にしていますので、ぜひ見てください。
先日、先生の工房の2階で見せていただいた作品ですね。
圧巻の存在感でした。
先生にとってもとても思い入れの強い作品と聞きました。
今回は、そのエピソードも含めてお聞きいたします。
こちらは、いつ頃に造られたのでしょうか?
毘沙門天さんは、四天王の中の一体で四天王になると多聞天(たもんてん)という仏さんです。
これは25歳の時に彫った仏像です。
こちらは模刻で、参考にしたものよりは一回り小さいものになります。
当時、私は毘沙門天さんを勉強させてもらいたいと思って、高野山の霊宝館に毎週日曜日に通って30cmぐらいの3分の1の原型を造らせてもらいました。
これがその時に私が彫っていたものです。
3尺にするための原型です。
私が持っている桧材の厚みも3分の1にしたものの板に賽の目状の線が、外側、内側にも全部書いてあって、その方眼できっちり合わせて膠(にかわ)でくっつけています。
それを容積分の木をまず作って、それで彫刻をどんどんどんどん進めるわけです。
彫り上げたら、膠でくっつけてあるのでバラバラにするのに釜に入れます。
そうすると膠が溶けて、こんな風な部材が出来上がるんです。
(このイラストはこの毘沙門天像の原型をバラバラにしたものとは異なります。参考となります。)
この賽の目を縦横で厚みも3倍にして材木の上に写していきます。
その輪郭を全部出して、それを一回くっつけて、彫刻すると大方の形が出てくる。
そこから綺麗に彫刻して仕上げます。
その仕上げたものが、あの毘沙門天なのですね。
そういう風に造るものなんですね。
この原型からは当時の先生の気迫の様なものを感じます。
当時、本当にようやったと思います。
一年に一体は必ず造らなきゃいけないというのがあって、私は一年でギリギリでもいいから、とにかく彫ろう思って、この本体と下の邪鬼を造りました。
彫り始めた当初、私はここまで腰をひねるつもりはなかったんですよ。
自分の印象で仏さんを選んで高野山に行ったのに、彫ってみるまでこの腰の動き、ひねりはちょっと私の中にはないなと思うぐらいひねっていました。
原型造りは、最初は3回現地へ通いで終わる予定だったんですが、それが7回もかかりました。
やっぱり自分の中でこの腰の動きなどの意識がなかったので造りようがなかったんでしょうね。
自分で造ってみたら、よく分かりました。
迷い刀というんですけど、悩みながら迷って彫っているのがこの原型にもいくつかあります。
体の軀体(くたい)をどうするかという自分の研究課題に直面させてもらったのがこの毘沙門天です。
こちらは鎌倉時代の平均身長になる様に造ってあります。
現代の日本人は、足が長く、腰高が時代に合っているのですが、 武将とか仁王さんの場合、腰高にしてしまうとどうしても力が入りにくいといったことも考えて造る様になりました。
原型を彫るのに、7回高野山へ通いました。
今やったらよう通いません、
なんぼ道が便利になったといっても(笑)
京都の桂を5時に出て、高野山に着いたら7時半、8時ですよ。
そこから彫り始めて、昼も取らずそのままぶっ続けでやって、日が陰って見えなくなるまでやってました。
その時に運転してくれたのが、一緒に勉強していた結婚する前の家内です。
大阪(自宅)からわざわざ京都(桂)まで来てくれて、私を乗せて高野山まで運転して、
そして、高野山から私を京都へ送ってから大阪の自分の家までの往復だけで7、8時間。
よう、やってくれたなぁと思って。
本当に面白い時期でした。
そんな中でできた毘沙門天さんだから、
そりゃぁ愛着もありますよ。(笑)
「あの四天王の毘沙門さん、好きやなー」
って思って行って、霊宝館の中でさすがに彫るわけにはいかないので、出たり入ったりして館の裏でコンカラコンカラと彫っているわけです。
で、その当時の館長が何か音がすると思って、裏に行ったら私が彫ってるわけです。
「ここで何をしとるの」って、
「勉強させてもらってます。京都で仏師を志しております。」と言ったら、
「うん、音がするのはいいけど、その直(地べた)に仏さんを置いて彫るのは、あまりよくない。ちょっと待っとれ。」って言って、
座布団持ってきて「この上でやりなさい。」って言ってくれたんですね。
私はもうてっきり
「とっとと帰れ。」
って言われるんかなって思ってました。(笑)
「出来たら、それを私にも見せてくれるかい?」って言ってくれていたので、出来上がってから「こういう風になりました」と写真を撮って霊宝館に持って行ったら、
館長さんが代替わりをしていて、報恩院(高野山)の方へ行って写真を見てもらうと 実物が見てみたいってことで持って行きました。
大きな仕事を任せてもらえるようになったきっかけは、この毘沙門さんが繋いでくれた縁です。
高野山との濃い縁をもらっています。
完成してから14、5年が経った頃、平成の大修理が高野山であった時に連絡がありました。
根本大塔の中に7、8mぐらいの坐った五智如来と大きな柱が16本あって、その柱に菩薩さんを描いた絵が巻き付けてあるんです。
これも修理して欲しいという話になって、
1枚がこの部屋に入り切らないぐらいの大きさの4mぐらいで、それが16枚ある。
「あんたとこに頼んだら、仏像の修理も画の修理も一緒にお願いできるから、別々にお願いをすると、仕立てをして完成した時に かち合ってしまったら、うまく立ち回りができないので、あんたところで全部仕切ってやって欲しい。」
となって携わったことも元を辿れば、
報恩院の先生が
「毘沙門天を彫ったあいつが、今独立してるらしいから それをちょっと呼ぼうか。」 と言っていただいて繋がった縁でした。
この毘沙門天を展覧会に何回か出展して、
これが欲しいって言っていただくお寺さんなどあっても、こう言ったんです。
「ダメです。」(笑)
何回もここに来て、それこそ10回といわんぐらいに何度も言っていただく方もいました。
ある日は
「今日は、もう(貰っ)て帰るぞ!」
またある日は
「今日は、トラックも人足も連れてきたから」
「お金もちゃんと持ってきたから。」
と現金を積まれたこともありました(笑)
何度も「ダメです。」とお断りしました。
それほど欲しいと言われても、
ここに置いておいたことには、
どんな理由があったのですか?
父親(義父)があの毘沙門天が大好きやったんですよ。
よく工房へちょこちょこ入ってきて、2階へ上がって見ていましたね。
私が彫刻をやってる時は、工房に来て横に座って見てました。
その父親の座右の銘が< 人に親切に >で、「いじめたり威張ったりすれば ろくなことにはならん」って、そればっかり言ってましたね。
こんな、いかつい顔した人に言われてもね。(笑)
当時私が、ことあるごとにお客さんを母屋に連れていって
中からガラガラーっと開けてお客さんが中を見ると、
「日本家屋やなぁ。」って言ってくれて、
「いや、ここは家内の実家です。」って言いながらも
我が物顔でみんなに見せるんですけれどね。(笑)
それも含めて、父親は、
楽しんでくれていましたね。
それが、嬉しかったですね。
ただの彫刻じゃないんですね、私にとってみたら。
「やっぱり工房に置かしてもらっていて 良かったなぁ」と思っていますね。
よく皆さんが昔から代々繋がっている京都へ行って依頼するっていうのは、長い信用があるからこそですね。
それを一から勝ち取っていけるほど甘い世界ではないです。
作品自体、安いものではなく、
それだけのお金をつぎ込むものですから、どんな人に、どんなところに住んでいる人が、どんな環境で彫ってくれるのかって思うのは、やっぱり当然だと思います。
母屋に連れて行って、家の中のしつらえを見て、造った作品を見て、それで彫るところも見せてというのをやっていくと
「あ、この人やったら確かに信用してもよさそうやなぁ」っていうことになってるんだと思います。
ここへ来てポンポンと筋がつながるっていうのは、工房の仏像を見てもらってからの話が一番多かったので、
この毘沙門天像と聖観音像が、その両翼を担ってくれたのだと思います。
あ、そうそう、家内と一緒になるきっかけの
高野山に行ったりっていうのも毘沙門さんきっかけだったしね。(笑)
師匠が「作った作品は、必ず動く」って言ってくれていました。
当時は "動く" っていう意味が分からなかった。
「縁を繋げに自分で営業みたいなことをやっても、なかなか繋がるもんやない。この仕事は。
作品が ちゃーんと繋いでくれるから。」
という言い方をしてくれていました。
この言葉は本当に身を持って分かりましたよね。
「だから、若い時にとにかく作りまくれ。」って、そういう言い方をしていましたね。
そのうちの一体です。
たくさんのつながり。
それをこの "動く" 毘沙門天さんが繋げてくれたんですね。
この参考は快慶作のものになりますか?
霊宝館の毘沙門天は、快慶さんの四天王ということで伝わっています。
その時、私はずっと運慶さんばっかり追っかけてきてたので、快慶さんの作品を模刻させてもらったのはこの毘沙門天が初めてです。
師匠は快慶の方が好きやったんですよ。
「わしゃ、運慶よりも快慶の方が腕が上やと思う。」
そこだけは、合わんかった。
若(宗琳)師匠はキュッとした緻密なところが好きで、それが快慶さんのいいところで、運慶さんは勢い。
松久朋琳、宗琳という親子は、ほんまに「動」と「静」が一つの工房の中に合体して居てはる天才やと思います。
あの天才は私はおらんと思う、すごい人やった。
師匠と一緒にお仕事をさせてもらって、弟子の間にその彫り口の云々も一つの工房の中で、お二人を同時に同じ時期に見られたので、本当に良かったですね。
あそこで12年、お世話になりました。
この作品は、いろんな機微(きび)になる仏さんの第一号で師匠に認められた作品です。
この腰をひねるというものの最たるもので、踊りでよくやる体型でもあり、野球の投球でもそうですね。
腰と胸がぐっと反って、これをバネみたいにして使って、手は後から出てきます。
同じ様に、足がこう、次に腰はこうで、肩は戻して、顔が前を向く。
仏像は全部にとにかく捻りが入っていて、順番にこうこうこう、それで直線を絶対に作らない。
左膝は折れているぐらい逆に曲がっている。
実際に人間の足もぐっと踏ん張ると後ろへ反るんです。
これが出来上がった時に初めて大(朋琳)先生※の方が褒めてくれて
「おぉ、この脚の配り、よう出けとんなぁ」
「だけどこれ、どっかで見たことあるな」
とか言うんですよ。
要するに模刻だと知ってるわけです。
「これを自分でオリジナルで、自分の作品で作れるようになったらいっちょまえ(一丁前)やなぁ」という風に言ってくれました。
いつもの大先生の感じは、
作品を見てもらっても
「ん、はい。はい、次。
ほぉー、うん、はい、次。」
そんな感じなんです。
だから、ほとんど話なんかしたことがない。
この毘沙門天を見せた時に
「明日から隣へ来い」って言ってくれて、
その次の日から本体を彫らしてもらう様になりました。
力強さ、勢い、情熱というのが伝わってくる作品で、
本当に先生の力が漲(みなぎ)っていると思います。
勢いで造る作品は、ある程度年齢がいった人には造れないと私は思います。
経験値と練り上げたものを造るのは、齢(よわい)を過ぎた方がやっぱりお客さんの声にマッチしたものを造りやすいと思うんですけど、そういうのは一切無視して、こと勢いっていう一点に絞るとやっぱり若い頃に造った方が勢いがあるかもしれない。
そう思いますよ、やっぱり。
だからこそ、その時にしかできない仏像っていうのが、やっぱりあると思いますね。
もし、この毘沙門さんの分身になるけれど、もう一体造るっていうことをやるなら、
その勢い、そのままをここに写することで、この時にやってた自分の体力から勢いからそのまま全部持って、ここにぶつけないとやっぱりあかんかなぁと思いますね。
だから今の私が彫るんじゃなくて、逆に当時の私と同い年ぐらいの弟子にとことん やらせてみて、その勢いでやった方が近いものが彫れるかもしれない。
工房の運営を考えた時に、依頼をしてくれた人になるべく近いものでお渡しするには、図面で出来上がって、こういうのを作ろうと決まったら、
最終的に手伝ってもらう子はこの子にしようっていうピンポイントで決めていきます。
なんで、この子にこれを任せるのって思うかもしれない。
でも、担当者を決めるっていうのは、やっぱり今までの経験を持った人たちの一つの知恵だと思っています。
その人の天職を見つけてあげるのは、そこに居てはった年配の方たちの目にかかってくる。
それが、結果になっているんですよね。
そういったことも含めて、この毘沙門さんが教えてくれていることは、今もあります。
この仕事と同じく、文化的な仕事をやってる能や歌舞伎の方々も、この子を女形(おやま)にしようっていうのを、小さい頃に最終的に決めるらしいんです。
その歌舞伎役者と親交があって、
一番最初の出会いの時に
私が仏像を造ってるって言うと
「へぇ〜、そうなの」
「じゃぁ、あんたも伝統的な仕事に携わっているのね、一緒やね」
っていう話をしてて、
「ちょっと、手ぇ見せてよ」
って言われてパッと手を見せたら
「はぁ〜、すごいね。ぶっさいくな手」
って言うんですよ。
「はぁ?」
って思ったけれどね。
続けて言ったのが、
「そこから 仏像が生まれるのね。
僕の手は こんなのなのよ」
「あんまり変わらんやん!」
って言ったら、
「だろう!」って(笑)
それで、
「ちょっと見とってな」
って言ってね、
踊ってくれたんですよ。
会って一発目で。
その手がむっちゃくちゃしなやかでね。
へえ〜と思って、
こーんな手で品(しな)を作れるもんなんやと思って。
「わかった? こんな手がね、
あんなんになるまで柔らかくなるのよ
これが伝統的な技よ」
って言っていましたね。
昔からあるもの、私たちも受け取らせてもらったんで、
だからこそ、受け取り方は色々あっていいと思うんですけど、次の人へ方策なりをなんとかして繋がなあかんと思っています。
今回は、私の一代記みたいになっちゃったね。(笑)
先生が受け継いできた大きさを改めて感じました。
また、その先生のお言葉をたくさんの方に伝える役目をしっかりと務めることの大切さにも触れられました。
私個人としては、先生の過ごしてきた人生と先のことまでのお話が聞けて嬉しかったです。
今回も、本当にありがとうございました。
※大先生…おおせんせい