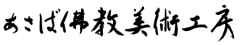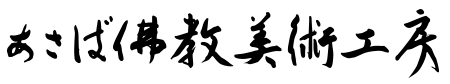対話形式の掲載にしていますので、ぜひ見てください。
今回は向吉先生の作品を通して、
聖観音についてお聞きします。
今回は聖観音についてお聞きします。
観音様とはどういった位の方なのでしょうか?
観音菩薩様。
菩薩という尊格(そんかく)は、如来(にょらい)になることが約束された方で人々に教えを説いて導く方です。
観音は三十三観音と言われて33種類あるのですが、
その中でも聖観音が私が一番好きで、この観音様に惚れてこの世界に入った仏様です。
聖観音は、今まで私が一番たくさん彫ってきたお姿で、
坐像(ざぞう)・立像(りゅうぞう)がありますが、
立ち姿が好きで、7割ぐらいを占めていると思います。
また私は木が好きで、木の素掘りの上に色を塗らず、漆を塗らず、素掘りのまま截金(きりがね)を入れているのが一番多いです。
これまで数多く彫ってきましたので、その思い入れも含めて今回はお伝えします。
こちらの聖観音像の特徴をお聞きします。
観音様のお姿は手を上げたり下げたり、脇腹と腕の間が閉じていたり開いていたりと様々で
アウトラインが同じではないのですが、全光背にするとその体の線が出なくなってしまいます。
そのため、この聖観音では宝珠形(ほうじゅがた)光背で頭の後ろだけについている光背にしています。
それから腰をぐっと捻っているところが大きな特徴です。
聖観音さんの場合は、こちらに歩み寄ってきてくださる姿で、このお姿は右足を前に出していますから、
出している足の逆の左の腰をぐっと捻った体の自然な流れを感じる様にしました。
すごくバランスがいいなと私なりに思ったこと、
そしてすごく練られてきた優雅さ、優しさ。
その魅力に取り憑かれてしまいました。
観音様は私にとって、
自分の中に一番ぐっと入ってくる、
素直にすーっと入ってくるストレートな方です。
その特別な観音様を先生が彫られる際、
心がけていらっしゃることはございますか?
「聖観音をお願いします。」と依頼をされた時に、もう既に10〜20種類の図面を用意しているんです、実は。
その全部を並べて「どれにされますか。」と尋ねると ものすごく迷われるんです。
そこでお話を聞いて、イメージされているのは こんなお姿かなっていうのを想像しながら、図面を2枚選びます。
「このお姿はどうですか。」と聞けば、
「これが、よろしいな。」と選んでいただけます。
そして、「この全体の立っておられるこの姿と、もう少し細めになった観音さんはこちらですが、どう思われますか。」と
更にを2枚お見せして、その時にピピッとくるものを選んでもらいます。
そこからすぐ彫っていく…
ではないんです。
それをもう一回アレンジします。
お堂が出来上がった状態の安置する場所、高さ、
それで、じゃあここはこうしましょうか、
お顔はこの高さまでにして、大きいのでお顔をもう少し下げましょうなど。
また、通常は宝冠(ほうかん)なども木で作るんですが、そのお堂が暗かったりした時には
ちょっと光るものがあった方が、お姿が浮き上がってくるといったことをイメージして、
宝冠を金具で作ったり、瓔珞(ようらく)といった少しお飾りを付けるといった提案もします。
こういったやり方にする前、
図面でのお姿の決定で仕上げてみると
「何か違う。」と
おっしゃる方がおられました。
今は図面で大体が決まったら、中のしつらえとか高さとかお好みとか、照明の強さ・当たり具合も、
工房の照明の切り替えをして、
「お堂の中はこれぐらいですか、これぐらいですか、これぐらいですか」と確認するようにしています。
それで、お顔の表情をちょっと優しくしたり強くするなども決めています。
観音様の像は安置している状況によって、表情がすごく変わるんですよ。
それを一番思い知らせてくれたのが、
こちらの等身聖観音(270cm)です。
この観音様を京都で最初に彫りました。
当初、この観音様の表情は私には厳しく映ったんです。
ですが、その時ちょうどコンクールがあって、出品した時にこの聖観音様の表情が当初の印象と違って、
とても優しく見えたんです。
その会場がものすごく明るくて、
「光というものが、これだけ見せていただく表情を変えるものなんだ。」と
光のマジックを知った瞬間でした。
そこから、観音様のいろんな表情は時代によっても異なってくるんじゃないかと考え始めました。
平安時代、鎌倉時代、室町時代と私の中では大きく分けると3つの違いがあるんです。
例えば、依頼主がお坊さんで修行してきた場所が高野山だったら、平安時代の仏像を拝んで修行している場合が多いんですね。
ですので、それを図面の中で表すなどしています。
だからといって、その時代に合わせたパターンで彫れば良いということではなくて、
さらに、その方の生い立ち、修行時代の思い出、苦しかった時に一緒に過ごしてくれた仏像のイメージはその方だけにある唯一のものだと思います。
その方の一生で拝む仏像。
思い入れ深いそのイメージに寄り添いたいとなったのは、この聖観音からです。
好きだからこそ、そして私自身にも思い入れがあるからこそ、真面目に練り上げてきたことが基礎になっています。
それほどまでに先生を魅了することになった観音様。
きっかけというのは、何があったのでしょうか?
滋賀県の渡岸寺(どうがんじ)観音堂の
木造十一面観音立像(国宝 像高177.3cm)
観音様で一番最初に好きになったのは、この方です。
お師匠さんから模刻で同じものを制作するようにと指示があって、滋賀県に行って4日間 お堂の中でエスキースといって原型を作らせていただきました。
その時、像の周りを回れて、正面から全方位をぐるーーっと見て、どの角度から見ても美しく、どこも破綻していなかったんですよ。
(破綻というのは、どこかの角度で「ここはもう少しこうした方がいい」と思う様なところがあること)
その様な経験は、この方が初めてだったんです。
人体をしっかりと感じることができて、
ほのかな色香がある。
すごくスタイルが良くて…
「うわっ、この人 好き!」
ってなって 彫った観音様は、この方が初めてなんです!
そこから、ますます のめり込んで、
運慶さんを辿ってみようと
愛知県の滝山寺(たきさんじ)聖観音菩薩立像(運慶造立)を見た際に、また惚れ込んでしまいました!
この方を自分の中に取り込んでお迎えしたいとなって造ったのが、先ほどの聖観音像です。
そこから十一面観音はこの方、聖観音はこの方、
と私の中のスタイルが確立しました。
どこから見ても美しい姿、
そこには彫り手が伝承してきたものはもちろん、
寄り添う心、そして「好き」「惚れる」といった人にとって とてもシンプルだけれど、大きなエネルギーが宿っている様に思えました。
1200年もの時を経た作品から先生が感銘を受け、
そして現代で新しく生み出されていくことの凄さを感じました。
観音様は彫り手にも夢を見させていただける仏様です。
お参りになって拝んで、何かを感じ取ってもらう方がいらっしゃればと思います。
先生、今回もたくさんのことを教えていただいて本当にありがとうございました。